サダオ、サウダージと共に生きた男
- yurizou24
- 2025年8月6日
- 読了時間: 11分
更新日:2025年12月31日

夜の都に吠える声
──大日本一誠会の影を追って──
2025年度 全国会議

第一章 新宿の狼たちの物語
昭和のはじめ、新宿の雑踏の裏に「万年東一」という名が轟き始めていた(敬称略)
京王線の線路伝いに歩くその姿を見ただけで、町の不良たちは道を譲った。
殴り合いで負けたことは一度もない。
「喧嘩は手段にすぎねぇ。本当の勝負は、人と人の間でつけるもんだ」
ボクシング部で鍛えた拳を武器に、大和拳闘倶楽部を立ち上げたとき、彼の周りには奇妙な男たちが群がった。
「人斬り小光」「ジャジャ馬の光」「オートンの勝」……異名を背負った愚連隊が、万年東一を頭目と仰ぎ、夜の街を駆け抜けていった。
第二章 戦後という闇
日本の戦争は終わった。
焦土と化した東京で、復員兵や浮浪者、ヤクザ、そして右翼の旗を掲げる者たちが入り混じり、新たな秩序を模索していた。
万年東一はその渦中に立ち、「大日本一誠会」を興す。
愛国を謳い、裏では企業と協力し、政治家と手を組み、時に街宣車を走らせる。
「声を上げることが力になるんだ。だが、声だけじゃ足りねぇ。金と人脈、そして恐怖も必要なんだ」
夜の銀座8丁目。
煌びやかなネオンの下、政財界の「闇紳士」たちと酒を酌み交わす東一の姿があった。
そこでは議会よりも重い約束が交わされ、金よりも高い「沈黙」が取引された。
第三章 雅叙園の宴
サダオの話になる。
目黒雅叙園。孔雀の羽を思わせる天井、漆塗りの廊下、豪奢な屏風。
そこに集うのは、政治家、財界人、そして東一をはじめとする右翼の男たち。
表の顔は祝宴だが、裏の顔は密談の巣窟だった。
第四章 電波の影
昭和も高度成長の時代へと移り、テレビ局が力を持ち始めた。
TBSの社屋の前には、時折、街宣車が並び、スピーカーからは怒号が響いた。
だが、その裏側では別の交渉が進んでいた。
「報道の自由もいいが、わかるか」
「……わかりました。ですが処理は慎重に」
封筒が動き、帳簿の裏に消える金。
その一部は「不正経理」として後に浮かび上がる。
テレビの電波に映るのはニュースだったが、その影で映らぬ物語が進行していたのだ。
第五章 闇に生きる者たち
地上げ、総会屋、右翼活動――すべては一本の糸でつながっていた。
夜の街でささやかれるのは「サダオや一誠会が動いた」という噂。
それは恐怖であり、同時に金脈を示す暗号でもあった。
サダオは酒をあおりながら笑った。
「俺たちは歴史に名を残すことはねぇ。だが、この街の血管を流れる血のように、生き続けるんだ」
闇は深く、誰もその終わりを見通せなかった。
ただひとつ確かなのは、戦後の日本という舞台で、大日本一誠会が確かに息づいていたという事実だけだった。
戦後の右翼の歩みについて
🏛サダオがともにした、万年東一氏と大日大日本一誠会の歩み
戦後という混乱の時代。
東京・新宿の裏路地には、血の匂いと酒の匂いがまだ濃く漂っていた。
そこから立ち上がったのが、愚連隊の頭目にして喧嘩師――万年東一である。
彼の歩みは、ただの不良の抗争に収まるものではなかった。
昭和44年、やがて彼は「大日本一誠会」を旗揚げする。
表向きは愛国を掲げ、裏では時代の裏街道を駆け抜ける集団であった。
東一は山形の寒村に生まれた。小学校の教頭を父に持つ、いわば真面目な家の次男坊だった。
だが、東京に移り住んだ少年は、京王線沿線の喧嘩場で次第に牙を研いでいく。
拳闘部で鍛えた腕っ節はすぐに評判となり、やがて新宿・渋谷・恵比寿――
あらゆる不良の頭目たちを従えるようになった。
「大和拳闘倶楽部」。
それはジムの名を借りた、実質は愚連隊の巣窟であった。
ここに集まったのは、人斬り小光、ジャジャ馬の光、小桜の秋、オートンの勝……異名を背負った若者たち。
彼らの刃が新宿の闇を彩り、東一の旗の下にひとつの勢力が生まれた。
昭和9年の夏。
雨に濡れた新宿の路地で、東一一派はついに宿敵・爆弾マッチこと山崎松男と激突する。
血しぶきが黒猫カフェの前に散り、刀が腕を切り落とし、短刀が腹を貫いた。
その夜、愚連隊はただの街の不良ではなく、“時代に抗う武闘派”として世に名を轟かせることとなる。
だが東一の進む道は、ただの抗争では終わらなかった。
右翼運動の旗手・千々波敬太郎との出会いが、彼を「思想」の世界へと導く。
光風塾に若衆を送り込み、喧嘩に飢えた若者たちはやがて“国家”を語りはじめる。
仲間は去り、裏切り、ある者は刑務所に、ある者は墓場に散った。
東一自身も裁判にかけられ、懲役を言い渡された。
だが、釈放の日。新宿二丁目の料亭「鳥源」には百名を超える子分が待ち構え、祝宴の酒が注がれた。
そこへ現れたのは――拳銃を携えた山崎松男。火鉢が飛び交い、弾丸が柱を抉る中で、命を賭けた和解劇が繰り広げられた。
その後の運命はさらに激動する。仲間の自殺、仲間の出征、そして上海での特務機関勤務。
そこで児玉誉士夫と出会い、彼の名は新たな裏社会と政界を結ぶ糸となってゆく。
こうして大日本一誠会は、単なる愚連隊の延長ではなく、戦後右翼の奔流を象徴する存在となった。
血で築かれた若者の誓いは、やがて「愛国」という衣を纏い、戦後の混迷の舞台にその影を落としていったのである。
昭和十五年の秋、上海の埃っぽい空気を振り払うように、万年東一は東京に戻ってきた。
戦火の匂いを纏った男の眼差しは、既にただの愚連隊の頭目ではなかった。
だが新宿の街は、彼を再びその懐に抱き込む。
銀座四丁目の喫茶店「不二アイス」。そこは夜ごと、煙草の煙と密談が交錯する愚連隊の溜まり場となっていた。
一方、新宿では「牡丹」と呼ばれる小さな喫茶店が彼の拠点であり、地元の者たちはそこを“地獄谷”と囁いた。
その頃、運命が万年にひとりの女を差し出す。
銀座の「ムーン」で働く睦美――後に彼の妻となる女性だ。
ふたりは東京・中野の小さな借家で暮らし始めた。
だが戦況は日に日に濃く、友である山田勇吉は北支戦線で命を落とす。
哀しみを飲み込みながら、万年は時代の奔流に飲まれていった。
やがて、召集令状。
昭和十八年、冬の新宿駅。
安藤昇と小林光也が見送る中、万年は軍服に身を包み、南支派遣軍独立歩兵第六十大隊へと送り出された。
山西省ワイヤン。そこは血と土が混ざり合う戦場であり、彼は華北交通の護衛として銃を握り続けた。
終戦。
昭和二十年十月、佐世保港に降り立った万年の眼前には、敗戦国の荒涼とした現実が広がっていた。
渋谷の闇市では、華僑総本部が闇の支配権を握っていた。
警察との衝突は避けられず、ついに「渋谷事件」へと発展する――街は再び血と怒号に包まれることとなった。
焼け跡の王者
昭和二十年十月。
佐世保港に降り立った万年東一の眼前には、敗戦の空が広がっていた。
風に吹かれる港の旗は、もはや「日の丸」ではなく、米軍の星条旗だった。
軍服を脱いだ東一が戻ったのは、かつて血と汗を流した東京。
だが、そこにあったのは廃墟と闇市だった。
渋谷・宇田川町。
瓦礫の隙間から芽吹くように闇市が立ち、華僑総本部がその支配権を握っていた。
彼らは禁制品を売り、不法建築を繰り返す。警察が取り締まれば、群れを成して抗議に押しかけ、
警官を袋叩きにする――やがて「渋谷事件」と呼ばれる抗争の火種となった。
東一はそこで戦友や旧き仲間を探したが、消息は途絶えていた。
ただひとり、再会の縁を結んだのは小池農夫雄の妻・治子。
「……農夫雄は、戦の途中で……」
彼女は小さなクラブで寿司を握り、逞しく生き延びていた。
だが、その笑顔の奥に、失った夫の影が消えることはなかった。
やがて再び小林光也と出会う。彼の傍らには、鋭い眼差しを持つ若者――安藤昇、そして加納貢がいた。
新宿から下北沢へ。戦後の東京では、愚連隊の勢力が新たに生まれ変わり、地盤を奪い合っていた。
昭和二十一年三月。下北沢の屋台での些細な衝突が、やがて血を呼ぶ抗争へと広がった。
黒木健児、野田克己ら下北沢グループが三田組の組員を叩き伏せ、
報復として沢野哲也が日本刀で野田を斬りつける。
背に深々と走る刀傷から血を流し倒れる野田――その夜、街全体が不穏にざわめいた。
だが、血で血を洗う抗争を収めたのも、また万年であった。
翌月、喫茶店「パール」。紫煙漂う狭い店内で、安藤と向かい合った東一は低く言った。
「これ以上は無駄だ。死人が出れば、皆ただの犬死にだ」
沈黙ののち、双方が頷き、三田組との手打ちが成された。
しかし東京の混乱は収まらない。
同年十月、産業別労働運動による「十月闘争」が吹き荒れ、新宿武蔵野館の映画館すら組合員に占拠される。
「東一さん、頼む。このままじゃ映画館が潰れる!」
社長に懇願され、万年は決断する。
小林が率いる舎弟五十人――その中には安藤の姿もあった――
が館を襲撃し、怒号と椅子が飛び交う中で組合員を力ずくで追い出した。
焼け跡の東京で、拳こそが秩序を作り出す唯一の言葉だった。
だが、その混沌のただ中で、東一の胸を裂いたのは、最も近しい者の死だった。
昭和二十二年、妻が肺結核で倒れた。
夜更け、布団に横たわる彼女の細い手を握りながら、東一はただ黙っていた。
戦場でも、抗争でも涙を見せぬ男の眼から、一筋の涙が静かに流れ落ちた。
彼は知っていた。己の歩む道には、光よりも闇の方が多いことを。
だがその闇を、誰かが切り裂かねばならない――そう信じていた。
総会屋としての顔
昭和二十三年。
新宿の料亭「松川」の座敷にて。
大企業の重役たちがひそやかに並び、東一は煙草をくゆらせていた。
「会社も人間と同じだ。弱みを突かれりゃ転ぶ。だが俺が守ってやりゃ、転ばねぇ」
彼の言葉に、経営者たちは恐れと安堵を入り混ぜた表情を浮かべる。
愚連隊の親分から総会屋へ――。
裏社会の頂点へ向けて、東一は階段を一段ずつ上っていった。
安藤昇との縁
同じ頃、安藤昇は「下北沢の若き首領」として名を馳せていた。
冷酷な眼差しを持ちながら、どこかインテリの風貌を漂わせる安藤に、東一は一種の親近感を覚えていた。
「安藤、てめぇは若ぇが、頭が切れる。俺とお前なら、この東京を牛耳れる」
安藤は笑みを浮かべてグラスを掲げた。
「万年さん、時代は変わる。だが、変わらねぇものもある――“力”だ」
その言葉に、東一は黙って頷いた。
右翼への傾斜
昭和二十四年。
講和の兆しとともに、街には再び「国家」「愛国」といった言葉が飛び交い始めていた。
東一は、その旗印に自らの道を見出した。
「俺は愚連隊の頭でも、総会屋でも終わらねぇ。日本を背負う“男”になってみせる」
その決意のもと、彼は信頼できる仲間を集め、組織を作り上げた。
場所は新宿。
名は――大日本一誠会。
設立の夜、東一は小さな神社に立ち、幹部たちの前で言った。
「俺たちは喧嘩屋でもチンピラでもねぇ。“誠”の二文字を背負い、この国のために立つ。
時代がどうあろうと、俺たちは退かねぇ」
その声に、仲間たちの眼が燃える。
街の不良少年から、戦場を経て、総会屋、そして右翼へ――。
万年東一という男の名は、この瞬間から戦後日本の暗部に刻まれることになった。

夜桜が舞い散る街で
運命の糸
昭和三十年、新宿の夜は煙草の煙と酒の匂いに包まれていた。
ネオンサインが踊る街角で、一人の若者が古いギターを抱えて歌っていた。
名前は北島太郎—後に「サブちゃん」と呼ばれることになる男である。
黒いスーツを着た男が足を止めた。安藤昇—渋谷を仕切る「安藤組」の若きリーダーだった。
「おい、ボウズ。いい声してるじゃないか」
安藤の声は意外にも優しく、太郎の心に温かく響いた。
「元気か?頑張ってやりな」
その言葉は、まるで兄が弟を励ますような響きがあった。
太郎は深々と頭を下げた。この出会いが、二人の運命の糸を紡ぎ始めた瞬間だった。
第三章 再会の舞台
昭和四十年代、太郎は「北島三郎」として演歌界のスターになっていた。
一方の安藤は、東映任侠映画の看板俳優として銀幕を飾っていた。
運命の再会は、映画『昭和残侠伝 破れ傘』の撮影現場で起こった。
高倉健、鶴田浩二らと共に現場入りした安藤の目に、脇役として出演していた北島の姿が映った。
「よう、サブちゃん。立派になったじゃないか」
安藤の呼びかけに、北島は感激で声が震えた。あの夜の渋谷での出会いが、こうして映画の世界で花開いたのだ。
「これからよろしくな」
安藤の握手は、かつてと変わらず温かかった。
浅草の夜
映画での共演がきっかけとなり、北島は浅草国際劇場での自身の公演に安藤をゲスト出演として招いた。一週間の特別公演は大盛況となった。
舞台袖で二人は語り合った。
「安藤さん、あの時の言葉がなかったら、今の俺はいなかった」
「何を言ってるんだ。才能があったから今があるんじゃないか」
二人の友情は、芸能界の華やかな世界でも色褪せることはなかった。
桜散る青山で
平成二十八年、青山葬儀所。安藤昇の「お別れの会」に、白髪の北島三郎の姿があった。
記者に囲まれた北島は、涙ながらに語った。
「渋谷で『頑張れ』と声をかけてくれた安藤さん。あの人がいなかったら、今の北島三郎はいませんでした」
春風が桜の花びらを舞い散らせる中、北島は静かに手を合わせた。
任侠と演歌—二つの世界を生きた男たちの、半世紀にわたる友情の物語は、こうして幕を閉じた。しかし、その絆は永遠に語り継がれることだろう。




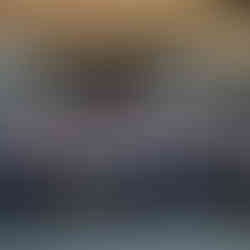






コメント